札幌でこの2、3年、フラットルーフでスガモリが起きるケースが増えているという。これまでは躯体の断熱・気密や小屋裏換気をしっかり行えば、スガモリの心配はないとされてきたが、現実にスガモリが発生している以上、さらに徹底した防水対策が必要との考え方が強くなってきている。ここで改めてフラット系屋根の防水を考えてみたい。

スガモリを起こして天井が濡れている住宅の例 |
スガモリの原因
気象の変化も関係?
「フラットルーフでスガモリが起こるようになったのは3年ほど前から。それまでは特に問題はなかった。以前は1日に集中して大雪が降ったり、1、2月に雨が降ることはなかったが、ここ数年はそういうことが起こっている。そのような気象の変化がスガモリの発生に関係しているのではないか」。
こう話すのは、ここ数年のスガモリ被害に悩む札幌市内のビルダー。断熱・気密性能に関しては高いレベルを確保し、小屋裏換気もしっかり行っているが、それでもスガモリが起きてしまったという。これまでは天井も含む躯体の断熱・気密・気流止めをしっかり行い、小屋裏換気を十分に取れば安全と言われてきたが、気象条件などにもよるがそれだけでは、スガモリを防ぎきれないのではないか、というのが問題の出発点だ。
フラットルーフのスガモリは、屋根面の融雪によって氷堤ができ、ハゼから融雪水が漏れることによって起こると考えられている。融雪の主な原因は小屋裏空間が暖まること。特に天井の断熱・気密が不足していると、室内から暖かく湿った空気が小屋裏に流れ込み、小屋裏結露を引き起こし、スガモリの原因をもつくる。また、道東などのように氷点下の外気温でも晴天が続くと、トタン面が暖まって融雪を促進することもある。
そのため屋根面の雪をできるだけ溶かさないよう、天井を断熱・気密化して室内の熱が小屋裏に入るのを防ぐと同時に、小屋裏空間を外気温に近い状態に保つために小屋裏換気を十分に行うことが必要とされている。
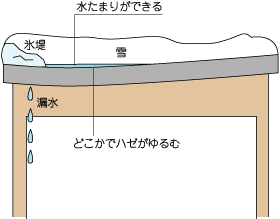
フラットルーフのスガモリは雪の重さで屋根面がたわむほか、軒先に氷堤ができて融雪水がたまり、ハゼがゆるむなどして小屋裏側に漏水すると考えられる |
特に小屋裏換気については住宅金融公庫の北海道版共通仕様書で、軒天有孔ボードを使う場合でも積層プラスチック換気部材を使う場合でも軒先全周に設置しなければならない。これは全国版共通仕様書の基準と比べても2~3倍の設置量で、屋根面の融雪防止のためには、いかに多くの換気量が必要かがわかる。
断熱・気密・換気に加え新たな対策が必要に
ここ数年で起こっているスガモリは、断熱・気密・小屋裏換気を十分に行ったうえで起きていると、ビルダーは口を揃える。
では原因は何か。今のところわかってはいないが、冬期の気象の変化を挙げる人は多い。最近、札幌では短期間に集中して大雪が降ったり、時には暖冬で雨が降ったりすることがあった。大雪によって一時的に積雪荷重が増えて屋根面がたわんだり、雨によって溶けた雪が凍る現象が起こっている。
原因はとにもかくにも、大切なのはスガモリ事故が起きている以上、さらに安全な防水を考えなければならないという点だ。
スガモリ(すがもれ):雪のある時期だけ、屋根から水が漏れる現象。一般的には雨もりと同様に扱われるが、専門家の間では分ける。スガモリを起こした家でも、夏場に雨もりは起きないケースがほとんど。水漏れが起きる原因が違うからだ。
すが漏れともいう。

|
|
 PDFファイルをご覧になるには専用の無料ソフト・Acrobat
Readerが必要です。 PDFファイルをご覧になるには専用の無料ソフト・Acrobat
Readerが必要です。
Acrobat Readerのダウンロードはこちらから |
|