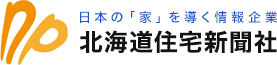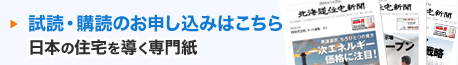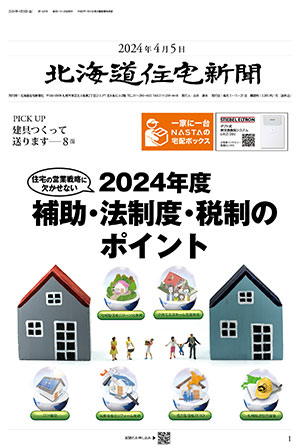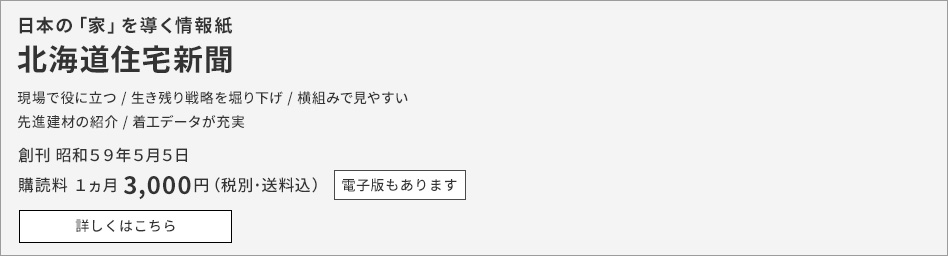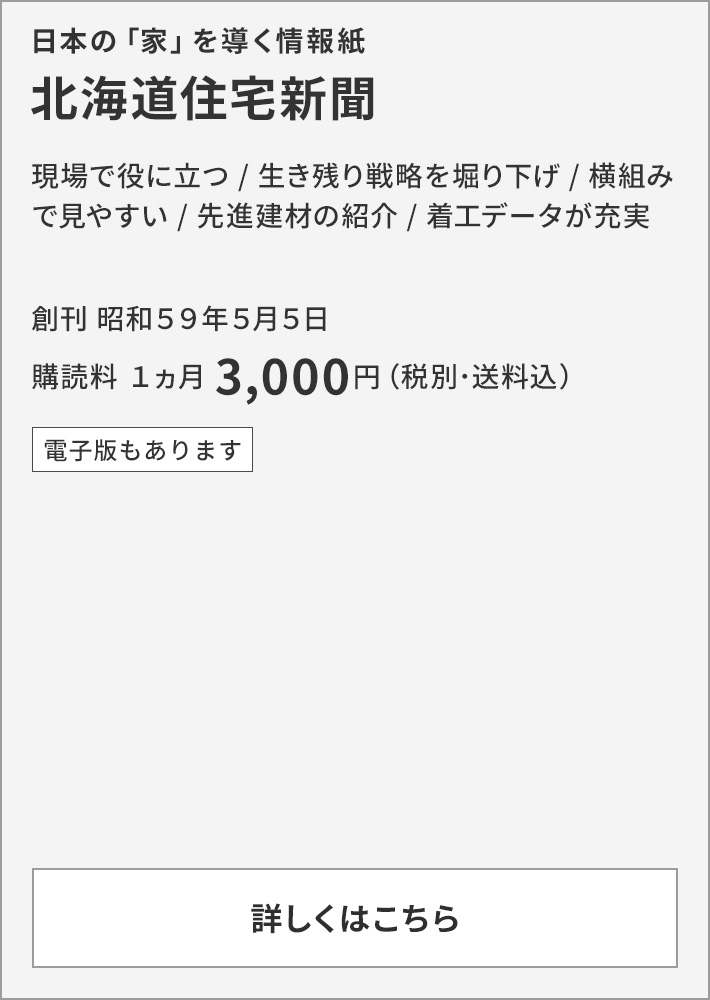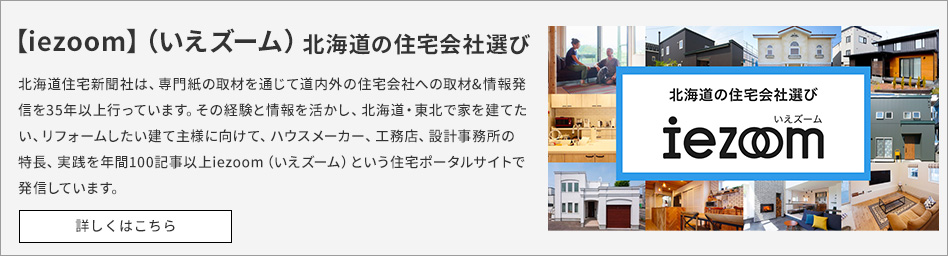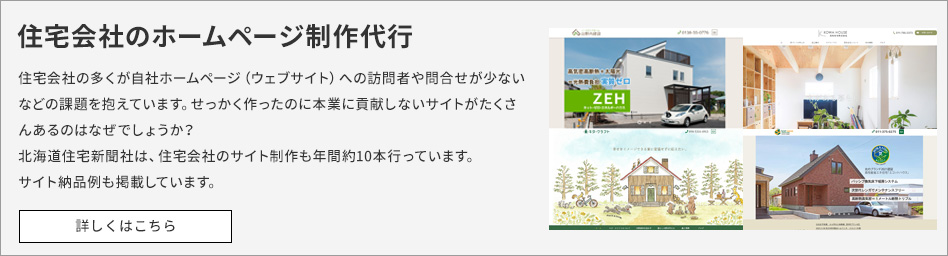道内でも太陽光発電を設置する住宅が増えつつあるが、記録的な大雪となったこの冬は、「パネルに雪が載って落ちない」「発電しない」「スガモリした」など、安心面での課題が出た。そこで安心できる太陽光発電をユーザーに提案するには、どのように設置すればいいのか。
注意点と対策を取材した。
*パネル上の積雪*
2ヵ月以上も発電ゼロが続く
 「北海道札幌市在住です。今年の1月下旬に三角屋根面(南向き)に太陽光パネル10枚設置いたしました。今現在、設置してから一度も発電はしておりません。おまけに雪は全く滑り落ちません。パネルが7枚ほど見えているのに、全く発電しなくて業者に連絡。回答は、回路が1系統のため、大切な部分(パネル)が隠れているのでしょうと...。そんな説明は設置する前は全くありませんでした。そうなると冬は雪も滑り落ちないし、発電も全くしない。おまけに室内のモニターの電源までは入らなくなりました。何故だろう。工事トラブル? 困ったもんです」。
「北海道札幌市在住です。今年の1月下旬に三角屋根面(南向き)に太陽光パネル10枚設置いたしました。今現在、設置してから一度も発電はしておりません。おまけに雪は全く滑り落ちません。パネルが7枚ほど見えているのに、全く発電しなくて業者に連絡。回答は、回路が1系統のため、大切な部分(パネル)が隠れているのでしょうと...。そんな説明は設置する前は全くありませんでした。そうなると冬は雪も滑り落ちないし、発電も全くしない。おまけに室内のモニターの電源までは入らなくなりました。何故だろう。工事トラブル? 困ったもんです」。
これは今年3月に弊紙編集長のブログに寄せられたコメント(一部改編)。雪が多かったこの冬は、同様のコメントがいくつかブログに書き込まれた。「パネル(モジュール)に載った雪が落ちない」「雪が載っているのは一部のパネルだけなのに発電しない」などだ。
なぜそのような状況になるのか? 積雪寒冷地で、パネルに雪が載るのはしかたないこと。ただ、晴天でも雪がなかなか落ちず、発電しない日が続くと、ユーザーの気持ちは複雑だ。
架台のをできるだけ高く
実際に雪が落ちない原因の多くは、パネルの傾斜角や方角、架台の高さにある。発電効率を考えれば、道内ではパネルの傾斜角が30~35度で真南に向けて設置するのが一番いいと言われる。しかし、落雪を促して冬期間にいかに発電させるかということを考えれば、フラット系屋根では40~45度、こう配屋根では6寸こう配以上の傾斜角がいいようだ。フラット系屋根の場合は、屋根上の積雪がパネルからの落雪を妨げないよう、架台の足をできるだけ高くすることも大切だ。
土屋グループで太陽光発電設置を行う㈱アーキテクノの藤原輝治常務は「当社では無落雪屋根の場合、パネルの傾斜角を45度、屋根面からパネル下端までの高さを80㎝~1mとしている。こう配屋根なら6寸、最低でも5寸のこう配はほしい。傾斜角が30~35度と40~45度の発電量の差は2%程度なので、いかに冬期に発電させるかを考えれば、雪が落ちやすい45度の傾斜角のほうがいい」と話す。
また、パナソニック㈱エコソリューションズ社北海道・東北電材エリアマーケティンググループの和田登参事は、屋根の形状や架台の傾斜角と荷重、方位などをトータルで考えることが必要と指摘。「当社では道内を垂直積雪量によって3つの地域に分類。それぞれこう配屋根、無落雪屋根、地上に設置する際のパネル傾斜角や架台の高さを設定することで、晴れればパネル上の積雪が落ちるようにしている」と語る。
1枚でも積雪あれば発電しない?
*雨もり・スガモリ*
*感電・漏電*
*施工品質の確保*
など続きは、以下のページから伝言欄に「4月25日号の見本も希望」とご記入の上、試読紙をお申し込みください
https://www.iesu.co.jp/publication/newspaper/